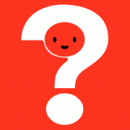「どうする?日本のお産」プロジェクト - [東京]午後のグループディスカッション Diff
- Added parts are displayed like this.
- Deleted parts are displayed
like this.
{{toc}}
◆[[グループワークの方法についてお読みください。|http://do-osan.socoda.net/#l4]]
!助産師が役割を発揮するには?
*HPが?出産費用を上げ、現在との差額分をゲーム会社が負担する
*HPが助産師の給料を上げる
*育児休暇明けの助産師再教育の場を国が設ける
*医師・助産師が後輩を大事にする
*医師会助産師会でお産のテーマパークを作る。
*医師が自然分娩の経過を待てる
*医師が助産院(助産師)をバックアップすることを苦に思わない
*医師が助産師の職能を認める
*医師は助産師の地位を認める
*医師も勇気を持って発言する
*一番売れている漫画家にお産(産科医・助産師)を書いてもらう(ドラマ化)
*医療機関が助産実習に協力する
*医療者は自主規制を発揮する。質を良くする
*大手証券会社は病院の院内助産院を全力でサポートする
*お母さんが助産師さんを助ける
*おかあさんが助産師を知る
*恩賜のお金を使って助産師養成所をつくる
*行政・病院は新米の助産師が力をつけるために就職できる場をつくる
*勤務助産師も地域へいく
*国が医療専門職の免許更新制度をつくる
*国が大点法で授乳室の設置を義務つける
*国が産科のある医療施設に定数化する
*国が残業手当を高く設定する(結果残業が出来なくなる)
*国は医療者に連続1ヶ月休暇が取れるようにする。
*雇用側が助産師を産科以外に勤めさせない
*産科医がつき1回助産師と飲み会をする
*自治会が各町の助産師を探しだし交流会を開く
*小学校のPTA活動で助産師さんの活動を知れるようにする
*商店街は子育てカフェをつくる(助産師のいる)
*助産師会が開業助産院の存在をアピールする
*助産師が開業する際に専属Drを国が派遣する
*助産師が仕事場で子連れで働く
*助産師が自分の意見を言えるように自分を鍛える
*助産師が新聞をつくる
*助産師学校が同窓会名簿から潜在助産師名簿を作る
*助産師学校の設立基準を見直す
*助産師学校の設立基準を見直すDrから認めてもらう為に実力をつける
*助産師が妊娠・出産する端子差を世間に知らせる
*助産師と医師はコミュニケーションを深める
*助産師はもっとアピールする
*助産師はもっとアピールする会陰切開縫合をする権利を取る
*助産師も疲れないようにする(労働基準)
*助産師を学校を増やす
*すべての都道府県が助産師学校をもつ
*正常助産は助産師が担当する
*西洋医学だけでなく東洋医療の知恵を教育(漢方・冷え等)
*潜在助産師講習会に託児サービスがある
*潜在助産師のリハビリ施設がシステムをつくる
*せんじあ
*大学から助産師家庭を外す
*中学校で助産師の職業案内をする
*妊産婦がお産を理解し、自分の出産に自信がもてる
*病院が専門職を認める
*病院が専門職を認めるスタッフの為にマッサージルームをつくる
*不動産屋さんは助産所を優遇する
*閉院する産院が開業すしたい助産師に場所を提供する
*ぺーパードライバー研修(助産師)
*ベネッセがベネッセ助産院を作る
*皆がお互いを尊重しあい助けあう
*みんなが出産の素晴らしさを伝える
*病院で、国で育児中の助産師もキャリアダウンしないようになシステムを(パートタイム)
*助産師がもっとTVに出る
*助産師が健診から診てもらう
*病院が開業助産所の嘱託医を引き受ける
*JRがすべての主要駅に助産院をつくる
*学校が実習時間を多くする
*助産師はニートを夫にする
*病院が勉強する時間費用をサポートする
!産む力、育てる力をつけるには?
*3食食べる習慣をこどものころからつける
*医者が不要な会陰切開をしない
*産む人が愛される(夫から・助産師から・両親から)
*産む人と家族が医療者とコミュニケーションをとって信頼する
*お母さんが自己管理をする
*夫が出産の時に妊婦のそばにいる
*お父さんがもっとお産のことをしる
*お父さんは17時退社する
*お父さんは1日1回家事をする
*お父さんは育児休暇を取れる。勇気を持つ
*おばあちゃんがお母さんに出産の話をする
*親達は命の話しを自分で出来る用になる
*お父さんはこどもをお風呂にいれる
*お父さんは職場の近くに家を持つ
*お母さんがリスクを認識する
*お母さんが初乳をんませられるよう努力する
*お母さんが病院・産み方を選べる
*お母さんどうし励ましあえるサークル作り
*お母さん予備軍が情報を集める
*会社は育児休業中の身分の保障をする
*教習所がカリキュラム中に産む、育てる関係を必修化する
*行政がすべてのトイレにオムツ替えシートを設置する
*国が母親の休暇日を設定する
*国が幼稚園・保育所の費用を負担することで経済的に体制を作る
*国はこどもを産んだ人が助産師になるための特別養成制度を作る
*厚生労働省の役人は1年間保育実習をする
*女性が自分の体を知る機会を作る
*女性が日頃から食事にきをつける
*女性も男性もお産や子育てについて勉強する
*ティーンエイジャーの雑誌社が妊娠出産について学べる記事を掲載する
*日本人の夫は妻にあいしてるよといつも言う。欧米のように
*母親がおっぱいで育てるという意識を持つ
*母親が出産体験発表をする
*母親は娘に食事をきちんとして体できるよう早寝・早起き・朝ごはんする
*病院が母親・両親学級の回数を増やす充実する
*ブライダルサロンは妊娠出産の情報を提供する
*保育所はお母さんの子育ての仕方を尊重する
*放送作家はドラマの出産シーンをあったかいものにする
*みんなが自分の体をいつくしむ
*みんなが食事を作れるようにする
*みんなが胎児にも声(心)があることを知る
*モーハウスがバーチャル出産体験を出来る施設・場をつくる
*若いお母さんが世の中は思い通りにならないと知る
*ワタミがつくる妊娠前に気軽に行ける産科医・助産師のいるカフェ居酒屋
*医者ががんばりすぎない
*一人っ子家族が兄弟たくさんいる家庭にお泊りする
*家族は三世代同居する
*会社は社員教育に出産教育を入れる
*学校が出産育児についての授業をする
*学校の教員が性教育をみなおす
*学校の授業で助産院へいく
*近所どおしが仲良くする
*国が小中学校で赤ちゃんの世話をする必須科目とする
*国が長時間労働には罰金
*国が病院にかかる人がへるほど、医師の報酬が上がる予防医療重視の制度をつくる
*国が母・家族が困ったときに人を派遣できるシステムをつくる
*国民が出産環境と子育てについて事情がわかる国会議員をたくさんつくる
*産む場所を自然の多いところにする
*市町村が学童児童を保育園であずかり、さまざまな年代と関われるようにする
*市町村が祖父母教室をつくる
*自治体がお産の学校をつくう
*住民どうしがよく会話をする
*助産師が地域にもっとでる
*助産師が保育師の教育にいく
*親が子供にいのちの大切さを伝える
*企業が専業主婦の夫にも育休を認める
*男の人がお産の大変さをもっと知る
*地域が駅前に子育て相談所をつくる
*地域が核家族を助ける
*地域が父親教育をする
*地域の人がお母さんたちをサポートする
*中学校高校が妊婦ジャケットをきるなど体験する
*中学高校が保育所訪問をし乳児と触れ合う時間をつくる
*中学高校生がベビーシッターをする
*みんなが日の出がみられるような生活をする
*任天堂が妊娠ー出産までロールプレイングゲームをつくる
*妊産婦は個々で体重コントロールをする
*妊婦さんが自分のカルテをもつ
*病院・行政が助産師の子供を預かれる場所をつくる
*病院・地域で産後の子供の発達育児について教える機械をつくる
*病院がお産のたちあいに子供をいれられるようにする
*病院が母子別室にしない
*不動産やさんが30戸以上の物件には託児所を義務化
*不必要なか会陰切開をしない
*夫がパートナーは妊娠したことがわかったら自分が産まれてきたことを聞いてみる
*夫も産む人も充分に育児休暇がとれる
*夫婦がお産のことを勉強する
*夫婦がなかよくする
!安全に安心して産むには? /仕事をするには?
*医師助産師が休日をしっかりとる
*医者が疲れないようにする
*医者と助産師が仲良くなる
*医療者がエビデンスに基づいた医療介入しかしない
*医療者がお母さんの産む力を信じる
*お母さんが自分をアピールする
*病院がお産する人が出産方法を選べるようにする
*医師助産師はお産プロセスを異常視しない
*お父さんは料理をつくり妻をサポートする力をもつ
*会社が、男性社員に育休を完全に義務化する
*企業は産前産後で本人・パートナーとも配置換えをしない
*行政が出産の多様性を知る
*行政は子を多く産んだ母に保育保障を出す
*行政はドクター・助産師・ナースを増やす
*国がお産の費用を無料にする
*国が親子教室を義務づけるシステムを作る
*国が粉ミルクを処方箋でしか買えないようにする
*国が産科医と小児科医と麻酔医と助産師がどの分娩にもついている体制づくりをする
*国が産科に関わる専門家に無過失保障をつける
*国が助産師の配置基準を決める
*国が中小企業に育休の補助金を出す
*国が妊婦健診を無料にする
*国が不要な分娩誘発をしたら罰金をとる
*国が分娩費用を高くする
*国が法律でつわり産休を完全に認める
*国が法律で不妊治療休暇を認める
*国が夜勤の助産婦が二名以上にする
*国と自治体が保育園の待機児童を完全解消する
*国は病院の集約化をしない
*クリニックが産婦人科の看板を明るくする
*警察が医療現場に入らない
*産科医。助産師の育休一年を義務化
*産科医が考えら得る時間をつくる
*産科医が待つ
*産科医研修で助産院実習をさせる
*産婦人科がいつでも手術できるようにする
*施設が壁をとりはらいネットワークを強化する
*自治体が専門職の人材バンクをつくり派遣をする
*社会が子連れでの仕事を認める
*国が出産一時金を一律ではなく所得によって金額を変える
*上場企業は医師・助産師・ナースを増やすことに協力する
*助産師が医師を助ける
*助産師が技術力をあげる
*助産師は母親によりそうということがどういう事かを知る
*女性社員が子育てと仕事の両立について具体的なのりきりかたの情報を知る
*女性達が産婦人科がかっこいいということをアピールする
*女性達が産婦人科がかっこいいということをアピールする
*すべての駅が子育て相談の場をつくる。
*地域がお産施設などの情報提供をする
*地域が地域に残ってくれた産婦人科医を支える
*地域や病院がパパの教室を積極的につくる
*内閣府の少子化対策と組んで予算の確保をする
*妊婦がセルフケアをきちんとする
*妊婦が身近な子育てサークルに足を運ぶ
*妊婦は他の妊婦の出産を見学する
*母が病院に情報公開を求める
*病院が情報公開をする
*病院が助産師の給料を上げる
*病院が働きやすい環境をつくる
*病院と助産所・診療所が懇談会を持つ
*病院は医者の待遇をよくする
*病院は女医を大切にする
*文化省が産科医助産師小児科医など周産期の大学をつくる
*本田先生が講演をする
*マスコミが出産の素晴らしさと厳しさの両面を伝える
*マスコミが日本の医療のいい面を正しく伝える
*マスコミが継続した取材をして、報道する。
*みんなが健康になる。
*メディアがお産とは何かをきちんと報道する。
*メディアが事実を伝える。
*レベルの高い医療機関は、どんな症例でも引き受ける。
*私たちが身内から産科医を出す
*医学教育か、正常産とか、健康をもっと教える。
*医師、助産師が休日をしっかりとる。
*医師が、やさしい言葉遣いをする。
*医師が、不要な開陰切開したら罰金。
*医師が、優しい目をする。
*医師がインターンシップ又は,学生実習で、助産院での実習を受ける。
*医師が助産師を、認める。
*医師と助産師が、お母さんと赤ちゃんが持っている力を信じる。
*医師の度量を、つける教育をする。
*医者は、妊婦の話を聞く
*家庭は、人を尊重できる人間をはぐむ。
*会社が、男性社員に育休を出す。
*会社は、男性職員に産休をとらせる。
*看護学生に、質のよいお産体験をさせる。
*看護師、医師は、産む人に自己紹介をする。
*企業が、社員のため社内産院をつくる。
*金持ち企業が出産施設をつくる(運営も含め)。
*厚生省の担当者が、助産所に合宿する。
*行政が、お産にかかわる人たちに補助金を出す。
*行政が、空ベットを確保する。
*行政が小さな産院をバックアップする。
*行政は県立(公立)の助産院をつくる。
*国が各地に母子センターを作る。
*国が女性省をつくりお産大臣を作る。
*国が保育園を増やす。
*国は、医療費全体を、バランスよくする。
*産科の医療報酬は、他科の2倍にする。
*産科医が、時間的に余裕ができる。
*産婦が専属助産師をつくり、どの施設でも付き添える受け持ち制を国がつくる。
*子供が、元気、健康でいる。
*市町村が産科が遠い産婦に無料で待機できる施設をつくる。
*助産師担当制にする。
*女性が自分の体を知る。
*女性は、男性体も知る。
*職場の人は、子供のために、仕事を休んだのを、怒らない.やすみをふやす。
*職場の仲間が、産後の仕事のサポートをする。
*正常産は、助産師が取り扱う。
*男の先生は、女の人のことを好きになる。
*地域が、お産を振り返る場を作る。
*地域の人、職場の人が協力して、保育所をつくる働きをすすめる。
*地市村が産院を設立する。
*妊婦は、しっかり健診を受ける。
*妊婦は、医者に話しをする。
*病院が、残業手当を100%だす。
*病院が24時間の託児室を設置する。
*病院がスタッフのために、マッサージルームを作る。ケアを受け放題。
*病院が助産師を他の出産施設で働くことを認める。
*病院が女性産科医のために24保育所を作る。
*病院のスタッフは、妊婦さん全員に会う。
*病院は、自宅で産めるシステムを整える。
*病院は、助産師スタッフの数を確保する。
*夫は、企業から出産休暇1週間、子育て応報休暇1ヶ月を必ずもらう。
*母親が、お産について知る。
◆[[グループワークの方法についてお読みください。|http://do-osan.socoda.net/#l4]]
!助産師が役割を発揮するには?
*HPが?出産費用を上げ、現在との差額分をゲーム会社が負担する
*HPが助産師の給料を上げる
*育児休暇明けの助産師再教育の場を国が設ける
*医師・助産師が後輩を大事にする
*医師会助産師会でお産のテーマパークを作る。
*医師が自然分娩の経過を待てる
*医師が助産院(助産師)をバックアップすることを苦に思わない
*医師が助産師の職能を認める
*医師は助産師の地位を認める
*医師も勇気を持って発言する
*一番売れている漫画家にお産(産科医・助産師)を書いてもらう(ドラマ化)
*医療機関が助産実習に協力する
*医療者は自主規制を発揮する。質を良くする
*大手証券会社は病院の院内助産院を全力でサポートする
*お母さんが助産師さんを助ける
*おかあさんが助産師を知る
*恩賜のお金を使って助産師養成所をつくる
*行政・病院は新米の助産師が力をつけるために就職できる場をつくる
*勤務助産師も地域へいく
*国が医療専門職の免許更新制度をつくる
*国が大点法で授乳室の設置を義務つける
*国が産科のある医療施設に定数化する
*国が残業手当を高く設定する(結果残業が出来なくなる)
*国は医療者に連続1ヶ月休暇が取れるようにする。
*雇用側が助産師を産科以外に勤めさせない
*産科医がつき1回助産師と飲み会をする
*自治会が各町の助産師を探しだし交流会を開く
*小学校のPTA活動で助産師さんの活動を知れるようにする
*商店街は子育てカフェをつくる(助産師のいる)
*助産師会が開業助産院の存在をアピールする
*助産師が開業する際に専属Drを国が派遣する
*助産師が仕事場で子連れで働く
*助産師が自分の意見を言えるように自分を鍛える
*助産師が新聞をつくる
*助産師学校が同窓会名簿から潜在助産師名簿を作る
*助産師学校の設立基準を見直す
*助産師学校の設立基準を見直すDrから認めてもらう為に実力をつける
*助産師が妊娠・出産する端子差を世間に知らせる
*助産師と医師はコミュニケーションを深める
*助産師はもっとアピールする
*助産師はもっとアピールする会陰切開縫合をする権利を取る
*助産師も疲れないようにする(労働基準)
*助産師を学校を増やす
*すべての都道府県が助産師学校をもつ
*正常助産は助産師が担当する
*西洋医学だけでなく東洋医療の知恵を教育(漢方・冷え等)
*潜在助産師講習会に託児サービスがある
*潜在助産師のリハビリ施設がシステムをつくる
*せんじあ
*大学から助産師家庭を外す
*中学校で助産師の職業案内をする
*妊産婦がお産を理解し、自分の出産に自信がもてる
*病院が専門職を認める
*病院が専門職を認めるスタッフの為にマッサージルームをつくる
*不動産屋さんは助産所を優遇する
*閉院する産院が開業すしたい助産師に場所を提供する
*ぺーパードライバー研修(助産師)
*ベネッセがベネッセ助産院を作る
*皆がお互いを尊重しあい助けあう
*みんなが出産の素晴らしさを伝える
*病院で、国で育児中の助産師もキャリアダウンしないようになシステムを(パートタイム)
*助産師がもっとTVに出る
*助産師が健診から診てもらう
*病院が開業助産所の嘱託医を引き受ける
*JRがすべての主要駅に助産院をつくる
*学校が実習時間を多くする
*助産師はニートを夫にする
*病院が勉強する時間費用をサポートする
!産む力、育てる力をつけるには?
*3食食べる習慣をこどものころからつける
*医者が不要な会陰切開をしない
*産む人が愛される(夫から・助産師から・両親から)
*産む人と家族が医療者とコミュニケーションをとって信頼する
*お母さんが自己管理をする
*夫が出産の時に妊婦のそばにいる
*お父さんがもっとお産のことをしる
*お父さんは17時退社する
*お父さんは1日1回家事をする
*お父さんは育児休暇を取れる。勇気を持つ
*おばあちゃんがお母さんに出産の話をする
*親達は命の話しを自分で出来る用になる
*お父さんはこどもをお風呂にいれる
*お父さんは職場の近くに家を持つ
*お母さんがリスクを認識する
*お母さんが初乳をんませられるよう努力する
*お母さんが病院・産み方を選べる
*お母さんどうし励ましあえるサークル作り
*お母さん予備軍が情報を集める
*会社は育児休業中の身分の保障をする
*教習所がカリキュラム中に産む、育てる関係を必修化する
*行政がすべてのトイレにオムツ替えシートを設置する
*国が母親の休暇日を設定する
*国が幼稚園・保育所の費用を負担することで経済的に体制を作る
*国はこどもを産んだ人が助産師になるための特別養成制度を作る
*厚生労働省の役人は1年間保育実習をする
*女性が自分の体を知る機会を作る
*女性が日頃から食事にきをつける
*女性も男性もお産や子育てについて勉強する
*ティーンエイジャーの雑誌社が妊娠出産について学べる記事を掲載する
*日本人の夫は妻にあいしてるよといつも言う。欧米のように
*母親がおっぱいで育てるという意識を持つ
*母親が出産体験発表をする
*母親は娘に食事をきちんとして体できるよう早寝・早起き・朝ごはんする
*病院が母親・両親学級の回数を増やす充実する
*ブライダルサロンは妊娠出産の情報を提供する
*保育所はお母さんの子育ての仕方を尊重する
*放送作家はドラマの出産シーンをあったかいものにする
*みんなが自分の体をいつくしむ
*みんなが食事を作れるようにする
*みんなが胎児にも声(心)があることを知る
*モーハウスがバーチャル出産体験を出来る施設・場をつくる
*若いお母さんが世の中は思い通りにならないと知る
*ワタミがつくる妊娠前に気軽に行ける産科医・助産師のいるカフェ居酒屋
*医者ががんばりすぎない
*一人っ子家族が兄弟たくさんいる家庭にお泊りする
*家族は三世代同居する
*会社は社員教育に出産教育を入れる
*学校が出産育児についての授業をする
*学校の教員が性教育をみなおす
*学校の授業で助産院へいく
*近所どおしが仲良くする
*国が小中学校で赤ちゃんの世話をする必須科目とする
*国が長時間労働には罰金
*国が病院にかかる人がへるほど、医師の報酬が上がる予防医療重視の制度をつくる
*国が母・家族が困ったときに人を派遣できるシステムをつくる
*国民が出産環境と子育てについて事情がわかる国会議員をたくさんつくる
*産む場所を自然の多いところにする
*市町村が学童児童を保育園であずかり、さまざまな年代と関われるようにする
*市町村が祖父母教室をつくる
*自治体がお産の学校をつくう
*住民どうしがよく会話をする
*助産師が地域にもっとでる
*助産師が保育師の教育にいく
*親が子供にいのちの大切さを伝える
*企業が専業主婦の夫にも育休を認める
*男の人がお産の大変さをもっと知る
*地域が駅前に子育て相談所をつくる
*地域が核家族を助ける
*地域が父親教育をする
*地域の人がお母さんたちをサポートする
*中学校高校が妊婦ジャケットをきるなど体験する
*中学高校が保育所訪問をし乳児と触れ合う時間をつくる
*中学高校生がベビーシッターをする
*みんなが日の出がみられるような生活をする
*任天堂が妊娠ー出産までロールプレイングゲームをつくる
*妊産婦は個々で体重コントロールをする
*妊婦さんが自分のカルテをもつ
*病院・行政が助産師の子供を預かれる場所をつくる
*病院・地域で産後の子供の発達育児について教える機械をつくる
*病院がお産のたちあいに子供をいれられるようにする
*病院が母子別室にしない
*不動産やさんが30戸以上の物件には託児所を義務化
*不必要なか会陰切開をしない
*夫がパートナーは妊娠したことがわかったら自分が産まれてきたことを聞いてみる
*夫も産む人も充分に育児休暇がとれる
*夫婦がお産のことを勉強する
*夫婦がなかよくする
!安全に安心して産むには? /仕事をするには?
*医師助産師が休日をしっかりとる
*医者が疲れないようにする
*医者と助産師が仲良くなる
*医療者がエビデンスに基づいた医療介入しかしない
*医療者がお母さんの産む力を信じる
*お母さんが自分をアピールする
*病院がお産する人が出産方法を選べるようにする
*医師助産師はお産プロセスを異常視しない
*お父さんは料理をつくり妻をサポートする力をもつ
*会社が、男性社員に育休を完全に義務化する
*企業は産前産後で本人・パートナーとも配置換えをしない
*行政が出産の多様性を知る
*行政は子を多く産んだ母に保育保障を出す
*行政はドクター・助産師・ナースを増やす
*国がお産の費用を無料にする
*国が親子教室を義務づけるシステムを作る
*国が粉ミルクを処方箋でしか買えないようにする
*国が産科医と小児科医と麻酔医と助産師がどの分娩にもついている体制づくりをする
*国が産科に関わる専門家に無過失保障をつける
*国が助産師の配置基準を決める
*国が中小企業に育休の補助金を出す
*国が妊婦健診を無料にする
*国が不要な分娩誘発をしたら罰金をとる
*国が分娩費用を高くする
*国が法律でつわり産休を完全に認める
*国が法律で不妊治療休暇を認める
*国が夜勤の助産婦が二名以上にする
*国と自治体が保育園の待機児童を完全解消する
*国は病院の集約化をしない
*クリニックが産婦人科の看板を明るくする
*警察が医療現場に入らない
*産科医。助産師の育休一年を義務化
*産科医が考えら得る時間をつくる
*産科医が待つ
*産科医研修で助産院実習をさせる
*産婦人科がいつでも手術できるようにする
*施設が壁をとりはらいネットワークを強化する
*自治体が専門職の人材バンクをつくり派遣をする
*社会が子連れでの仕事を認める
*国が出産一時金を一律ではなく所得によって金額を変える
*上場企業は医師・助産師・ナースを増やすことに協力する
*助産師が医師を助ける
*助産師が技術力をあげる
*助産師は母親によりそうということがどういう事かを知る
*女性社員が子育てと仕事の両立について具体的なのりきりかたの情報を知る
*女性達が産婦人科がかっこいいということをアピールする
*女性達が産婦人科がかっこいいということをアピールする
*すべての駅が子育て相談の場をつくる。
*地域がお産施設などの情報提供をする
*地域が地域に残ってくれた産婦人科医を支える
*地域や病院がパパの教室を積極的につくる
*内閣府の少子化対策と組んで予算の確保をする
*妊婦がセルフケアをきちんとする
*妊婦が身近な子育てサークルに足を運ぶ
*妊婦は他の妊婦の出産を見学する
*母が病院に情報公開を求める
*病院が情報公開をする
*病院が助産師の給料を上げる
*病院が働きやすい環境をつくる
*病院と助産所・診療所が懇談会を持つ
*病院は医者の待遇をよくする
*病院は女医を大切にする
*文化省が産科医助産師小児科医など周産期の大学をつくる
*本田先生が講演をする
*マスコミが出産の素晴らしさと厳しさの両面を伝える
*マスコミが日本の医療のいい面を正しく伝える
*マスコミが継続した取材をして、報道する。
*みんなが健康になる。
*メディアがお産とは何かをきちんと報道する。
*メディアが事実を伝える。
*レベルの高い医療機関は、どんな症例でも引き受ける。
*私たちが身内から産科医を出す
*医学教育か、正常産とか、健康をもっと教える。
*医師、助産師が休日をしっかりとる。
*医師が、やさしい言葉遣いをする。
*医師が、不要な開陰切開したら罰金。
*医師が、優しい目をする。
*医師がインターンシップ又は,学生実習で、助産院での実習を受ける。
*医師が助産師を、認める。
*医師と助産師が、お母さんと赤ちゃんが持っている力を信じる。
*医師の度量を、つける教育をする。
*医者は、妊婦の話を聞く
*家庭は、人を尊重できる人間をはぐむ。
*会社が、男性社員に育休を出す。
*会社は、男性職員に産休をとらせる。
*看護学生に、質のよいお産体験をさせる。
*看護師、医師は、産む人に自己紹介をする。
*企業が、社員のため社内産院をつくる。
*金持ち企業が出産施設をつくる(運営も含め)。
*厚生省の担当者が、助産所に合宿する。
*行政が、お産にかかわる人たちに補助金を出す。
*行政が、空ベットを確保する。
*行政が小さな産院をバックアップする。
*行政は県立(公立)の助産院をつくる。
*国が各地に母子センターを作る。
*国が女性省をつくりお産大臣を作る。
*国が保育園を増やす。
*国は、医療費全体を、バランスよくする。
*産科の医療報酬は、他科の2倍にする。
*産科医が、時間的に余裕ができる。
*産婦が専属助産師をつくり、どの施設でも付き添える受け持ち制を国がつくる。
*子供が、元気、健康でいる。
*市町村が産科が遠い産婦に無料で待機できる施設をつくる。
*助産師担当制にする。
*女性が自分の体を知る。
*女性は、男性体も知る。
*職場の人は、子供のために、仕事を休んだのを、怒らない.やすみをふやす。
*職場の仲間が、産後の仕事のサポートをする。
*正常産は、助産師が取り扱う。
*男の先生は、女の人のことを好きになる。
*地域が、お産を振り返る場を作る。
*地域の人、職場の人が協力して、保育所をつくる働きをすすめる。
*地市村が産院を設立する。
*妊婦は、しっかり健診を受ける。
*妊婦は、医者に話しをする。
*病院が、残業手当を100%だす。
*病院が24時間の託児室を設置する。
*病院がスタッフのために、マッサージルームを作る。ケアを受け放題。
*病院が助産師を他の出産施設で働くことを認める。
*病院が女性産科医のために24保育所を作る。
*病院のスタッフは、妊婦さん全員に会う。
*病院は、自宅で産めるシステムを整える。
*病院は、助産師スタッフの数を確保する。
*夫は、企業から出産休暇1週間、子育て応報休暇1ヶ月を必ずもらう。
*母親が、お産について知る。