[札幌]健康な妊婦・産婦だって不安はいっぱい!心とからだ、どう支える?
- 妊婦が自分の希望を主張する。
- 妊産婦が自分の身体を知る。
- 産む人が勉強する。
- 妊産婦が意識を変える(大きい病院だといいと思っている)
- 妊婦自身が集える仲間をつくる。
- 私が自然なお産をする。
- 私が大きな病院でお産する。
- 妊婦が勇気ももって発言する。
- 妊産婦が他力本願をやめる努力をはじめる。
- 妊婦さんがいつも笑っている→まわりがあたたかいサポートをする。
- 妊婦同士がつながりをもつようにする。
- 産婦が情報交換をする。
- ママが幸せになる。
- 私たちは思ったことを伝える。
- 自分がNOという。
- 妊婦が経験者に話を聞く。
- 妊婦サークルがネットワークを持つ
- ママがパパを自慢する。
- 産婦が育児支援センターに行く
- 産婦が知識経験をもっと勉強する。
- 私が幸せに生きる。
- 自分が妊娠中にたくさん体力づくりをする。
- 日本の女性がわがままになる。
- パパがママを子どもを自慢する。
- 夫が育児休暇を絶対取る。
- 夫が出産に立ち会う。
- 夫婦が望む形で育児休暇を取る
- 夫が健康を保つ
- 夫が妻とコミュニケーションをとる
- 夫が家庭の中のことを自立してやる(できることは自分でする)
- 夫が家事を手伝う。
- 夫が家事をする。(2)
- 夫が仕事を休む。(2)
- 夫が早く家に帰る、残業やめる。
- 夫が優しい言葉をかける。
- 夫が支える
- 夫が話を聞く(2)
- 夫の会社は積極的に休みを取らせる。
- 夫がマッサージをする。
- 夫が妻を支える
- 夫が(妻も)妊娠・分娩を学ぶ
- 親族(お産経験者)が「大丈夫だよ」と言ってくれる。
- 家族が話を聞く。
- 家族・周囲が意識を変える。
- 夫以外の家族もよく話を聞いてあげる
- 妊産婦の親が手伝う。
- 親が妊婦に話をする。
- 家族(実父母、姑など)が妊娠・出産を学ぶ
- 家族が助ける
- 地域のおばあちゃんが妊婦さんの相談にのる。→そのための助産師が妊婦の相談にのるにための数がたりない→クニが助産師の教育を変える。
- 私たちが情報共有・提供の場、先輩ママさんなどとの交流の場をつくる→地域での子育て意識の変革
- 町内会が妊産婦の情報を持つ。
- 町内会が助産師を育成(居住)する。
- おばあちゃんボランティアチームが若いお母さんの援助をする。
- 社会が妊産婦さんが支えてほしい人(助産師など)を支える
- 経産婦が相談にのる。
- 地域の出産経験者が相談にのる
- 出産した人が妊娠中の人の相談にのる
- 妊婦OGが相談相手になる。
- 助産師がやさしくむかえる。
- 助産師がスキルアップする
- 助産師が不安を受け止める
- 助産師が、妊婦に情報を提供する。
- 助産師が増える。
- 助産師が時間をかけて話を聞く
- 助産師が相談にのる。
- 助産師会相談会を設ける。
- 助産師が地域に相談所を作る。
- 助産師が地域にいる。
- 助産婦が伝える。
- 妊婦の母が援助できるように助産師が母を教育する。
- 助産師が妊婦をサポートできるために行政が助産師をサポートする
- MWば継続的なケアを提供する。
- MWがもっとゆっくり話を聞く(時間をもつ)
- カウンセリング専門家が相談にのる。→そのためには適切な団体がカウンセラーを養成する。
- 相談会を身近なところでこまめに
- 区の保健センターが妊婦に情報を提供する。
- 保健センターが妊婦相談会を増やす。
- 妊産婦をサポートするために専門家集団のネットワークをるくり相談窓をつくる
- 保健師が家庭訪問する
- 医療者がお母さんと赤ちゃんと引き離さない。
- 医療者が優しくかかわる。
- 医者が話を聞く。(2)
- 病院が妊婦さんの滞在先を確保する。
- 病院が妊婦が相談できる場をつくる。
- 医者が言葉を尽くして親身になる。
- 地域の医療機関が月に1回相談日を開く
- 病院が産婦の復帰支援をする。
- 先生が時間をかけて話を聞く
- 病院が産科と婦人科を分ける
- 医療者が情報を提供する。
- 職場が妊婦に対する理解を深める。
- 職場が子育てに対する(休みをつくる等)支援をする。
- 仕事が安定する。
- 給料が上がる。
- 若者が早く結婚する→仕事が安定する、育児が「かっこよく」なる。
- 企業が妊婦をサポートする
- 企業は産休、育児休暇をとれるよう努力する。
- 母子支援業者がカウンセリング、ベビーシッター、家事、サークル活動をアピールし、お母さんたちが活用できるようにする。
- 子どもが外で遊ぶ(自然の中で)→地域の安全を守る。
- 赤ちゃんが泣かない。
- 赤ちゃんがたくさん笑う
- 女性(男性も)よいお産について知る。
- 学習会には夫婦で参加
- 早く学校が性とお産についての教育を行う。
- 国は産休・育休を企業がとれるよう義務付ける
- マスコミがマイナスイメージの報道ばかりするのをやめる。
- 行政は妊婦のコミュニケーションがとれるような働きかけをする(場を提供する)
- 行政が相談TELを設ける
- 国が妊婦をサポートする企業の税金を優遇する
- 行政が若者に産科を見学させる。
- 保育園が増える。
- 私たちがすべてが水上案をすすめる。
- みんながNOと言う。
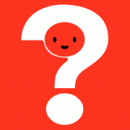











Keyword(s):
References:[[札幌]ご参加ありがとうございました] [終了した大会]