[埼玉]午後のグループワークまとめ
5人程度のグループに分かれ4つのテーマの中から一つを選んで話し合いました。 各グループが話した内容から、これは!という3つの意見をA4の紙に書いてもらい、 各テーマの模造紙に張り込んでいきました。
健康な妊婦・産婦だって不安はいっぱい。心と身体どう支援する?
不安への援助
- 妊娠が肯定できるまなざし、メッセージを社会が送る。
(「体の変化」は良いこと。「妊婦って美しい」など)
- 「不安になるのが当たり前。不安で良いんだよ」というメッセージを受け取る。
- 産んだ人たち(先輩ママ)が後輩ママのサポート
子どもへの教育
- 子どもたちに「命の大切さ」「産み育てることの楽しさ」を伝える。
- 成人式の後に「生と性の教育」を行う。
- 学校でお教育。中学校に学校助産師を!
環境(医療施設)
- 助産外来の充実(漠然とした不安もゆっくり話せる)
- 正常出産は助産師中心に院内助産院を開設
- 妊娠から出産・育児まで受け持ち制のケア(オープンシステムいいなぁ。)
- 病院・産院の待合室をカフエテラス風にして、そこにカウンセリングの先生もいる。
環境(地域)
- 男性にも妊産婦を支えるための勉強会を義務化
- 駅前に夜遅くまでやっている「まちの保健室(母子相談室)開設
- 母子手帳の交付と同時に地域の出産情報資料を配布(サイト・本・サークルetc)
- 出産から育児までいろいろな人といろいろな話しや体験ができる「交流の場」
- 「働いている私」も大切。産休に入ってから(9〜10ヶ月)の母親学級
- 経済的な援助の増額。Ex)第1子60万 第2子50万 第3子40万
緊急時の対応・体制どうする?
救急システム!
- 急変時のための空床確保。母児ともにバックトランスファーがある。
- NICU、産科三次救急システムをキチンと。(埼玉がんばれ!)
- 緊急時に搬送できるヘリコプター、Dr.ヘリを充実させる。
- 救急車に産科医、助産師が乗って搬送
救急時のケア
- 救急ほど心のケアを大切にして余裕ある対応
- 「一番よい方法で出産できることを考えます」と医師が妊婦・家族に説明する。
(自然出産だけが良いお産ではないことを伝える)
- 正常産と異常産の認識をし直す。
妊婦の身体作り
- 救急にならないような体づくりの教育を。
- 出産のすべてが救急、異常という呪縛を解き、自分の身体を信じる。
- 産む側も学んで自己管理。医療側も正常産を異常産にしない。
- 妊婦が、医療関係者が考える「緊急」「急変」の中身を知る。
- 出産は「母も子も死ぬこともある」という真実を医師が伝える。妊婦・家族は“産む”ことへの覚悟ができる。(生まれる)
社会的整備
- お産は一部の人ではなく、地域社会全体の問題(政治的問題)
- 何キロ四方にひとつ病院を造る法律
- 各自治体に国公立のバースセンター(院内助産所)が増える
- 救急も受け入れられるような施設、NICUは公立にして整備
- 自宅や助産所出産予定の妊産婦の連携先(病院)は妊婦が決め、受け入れてもらえる。
グループワーク後の全体ディスカッション
〜私がしたいこと、私ができること、そんなみんなの意見です〜
グループワークの後、4つのテーマの発表も終わり、その意見をもとに全体ディスカッションを行いました。
- 搬送先で楽しい分娩はできるか?まずは、話し合いの場作りを実行したい。
- 「お産は自然なこと」と周りの人に伝えたい。
- 次世代の人たちに、身体の神秘等を伝える誕生学アドバイザーを行っている。
- 自分の身体の仕組み(生理等)を知らない人が多い。女性がもっと知識を持つことが大切。
- 妊娠前の女性にも、お産の情報提供の場を。どんな出産をしたいか、どんな育児をしたいのかを考えるきっかけをもてるように働きかける。
- 子どもを産み育てたくない社会になっている。出産が人生において損ではないということを伝えていきたい。
- 本当の少子化対策とは何かと考えている。地域で関係性の構築と価値観を変えること、お産をしたい街、子どもを育てたい街にする。
- 急変時の対応は、助産師、助産院が病院への正しい搬送の仕方を守り、ガイドラインの徹底に心がける。
- 助産師情報(こんなことできる、紹介)を伝えていきたい。
- 妊婦サロンを(こんな所で産めます、出産情報)今年度開く。
- 産後は育児の情報はあるが、母親の身体についてのケアがない。産後フィットネスを広め、体力的にも精神的にも育児に自信が持てるようにしたい。
- 家庭的なお産を目指しているが、産科は救急が必ずある(特異なケースがある)それは避けられない事実。産科医は、ハイリスク、ハイリターンなもの。
- 助産師、産科医が連携をとることがよい。
- 地域・家族・産業構造が変わって、産科医になる人が少ない(医学部卒業生8000人中300人しか産科医はならない)出産場面に立ち会える感動を医学生にも伝えたい。
- 2人目の助産院で出産した子を、夫(カメラマン)がドキュメンタリーとして撮った。出産、助産師の活動について写真展を開いていく。
- 助産師さんへ開業しましょう!
- 看護師に比べ、お産の時に助産師の責任の重さを感じた。
- さらに、地域で自宅出産に出て、産科の医師の大変さを痛感した。(責任を負うこと)
- 助産師には、オプションではなく開業権があることを自覚して開業しましょう。
- ここでのもらったエネルギーや考え方を行政の中でも生かしていきたい。
できることを行動してほしい
- 産科医師の不足、出産場所の閉鎖は緊急なので、やってほしい、あってほしいでは遅い。
- 「欲しい」はやめて、それを実現することを行動に起しましょう。
(新聞に投稿する、議員さんに投票する、話し合いの場をつくる、いろいろな世代の人たちと語り合うなど今の自分に出来ることを感じて、考えて、見つけて、行動しましょう。)
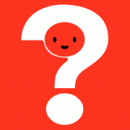











Keyword(s):
References:[終了した大会] [[埼玉]ご参加ありがとうございました]